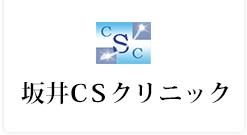免疫活性化血管内治療症例の紹介
転移性肝がん(てんいせいかんがん)
転移性肝がんとは原発巣から遠く離れた肝臓にがんが転移した状態をいいます。この状態はステージ4といい、末期がんであることを意味します。遠い臓器に転移する遠隔転移は、がん細胞が血流に乗って移動でき、新しい臓器に漂着するとそこで根を張って活動を開始したことを意味し、がん細胞が活発に活動を開始したと判断できます。このため肝臓転移を起こした状態のがんはステージ4に分類されます。
胃、大腸、膵臓などの消化器を流れた血液は、門脈という血管に集まって肝臓を通過してから心臓に戻るため、消化器のがんが最初に遠隔転移する臓器が肝臓です。肝臓への転移巣をここでくい止めておけば、病気が拡がることを防げます。抗がん剤を使わない免疫活性化血管内治療は転移性肝癌のがん患者に有効な治療法です。肝臓の転移病巣を殺すだけでなく、免疫細胞を活性化させ、転移しようとしているがん細胞も攻撃しやすくさせるため、新たな転移を防ぐことができます。
免疫活性化血管内治療はさまざまな原発巣から肝臓に転移したがんが、かなり進行しても適応できることが分かっています。正常な肝細胞への影響が軽微であるため他の治療法で効果がなかった末期がんの治療にも大いに期待できます。
治療症例1 肝転移の症例
大腸がんで手術された6ヵ月後に肝転移が見つかり、約1年後に当院、血管内治療を希望され来院されました。計3回の血管内治療を経て、腫瘍内部に濃染を示さない壊死領域の拡がりを認めるようになり、外来通院にて治療中です。
治療症例2 GISTの肝転移の症例
GISTの手術後に肝臓と骨に転移がみつかりました。グリベックやスーテントなどの新しい分子標的治療薬を投与されましたが、効果がなかったため、当院へ来られました。 治療前は肝臓に転移した腫瘍内にも血液の取り込みが認められましたが、 治療後は腫瘍の縮小と腫瘍内部への血液の取り込みを示さず、低濃度化しています。グリベックやスーテントと作用機序が異なるため、治療効果が現れたものと考えられます。
治療症例3 転移性肝がんの症例
病院の検査で肝臓転移が見つかりました。
腫瘍マーカー(CEA)が2回の治療で正常値まで顕著に激減。治療終了後1年後も腫瘍マーカーの上昇は認めていません。
副作用でお悩みの方は、坂井CSクリニックへ 免疫治療、抗がん剤を使わない血管内治療、遺伝子治療によるがん治療