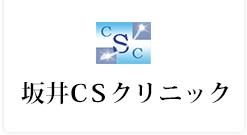免疫活性化血管内治療症例紹介:移植後の肝細胞癌
肝硬変や肝ガンのために新しい肝臓を移植するのが肝臓移植です。 肝臓移植を受けられたあとに、移植後の新しい肝臓に残念ながら再び肝細胞がんが出現してしまう方がおられます。免疫が抑制されているため癌が出来やすい状態になっています。がん治療のために肝臓の移植を受けたわけですが、結果は皮肉なことになっています。
症例1 移植後の肝細胞癌症例
肝臓移植をされたのち、肝細胞癌が見つかる。
検診にて異常を指摘される。精査の結果肝細胞癌といわれた。生体肝移植をされたのち、3年後に肝細胞癌が見つかる。約2年後に当院、活性化リンパ治療を希望されて来院。計2回の血管内治療と4回の活性化リンパ球治療を経て、腫瘍内部に濃染を示さない壊死領域の拡がりを認めるようになりました。
本来自分のものでない臓器を体内に移植するのですから、移植を受けたからだの免疫細胞は自分と異なる生物体が体内に入ったとして排除しようとします。これが拒絶反応です。
拒絶反応とは元をただせば正常な免疫細胞の仕事なのです。しかし、せっかく移植した新しい臓器が免疫細胞の攻撃を受けたら元も子もありません。このため免疫抑制剤を服用することになります。
免疫抑制剤とは、その名の通り免疫を抑えることによって拒絶反応をおこさないようにする薬です。
移植後は免疫反応をおこさないように免疫抑制剤を使用せざるを得ず、免疫を活性化させるのは困難になっています。抗がん剤を使わない免疫活性化血管内治療は免疫細胞を活性化させ癌細胞を攻撃しやすくさせるため、免疫低下状態のがん患者には有効な治療法です。一回の治療でかなりの量のがん細胞が死滅します。
副作用でお悩みの方は、坂井CSクリニックへ 免疫治療、抗がん剤を使わない血管内治療、遺伝子治療によるがん治療